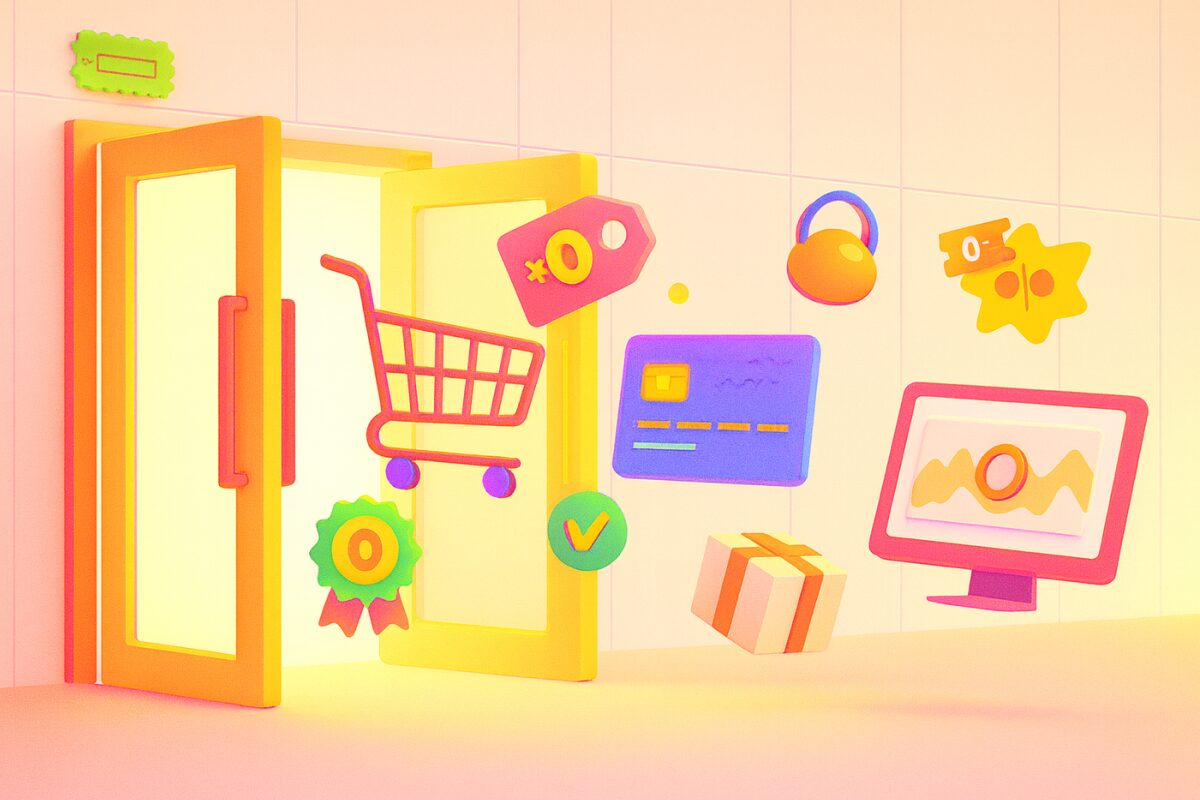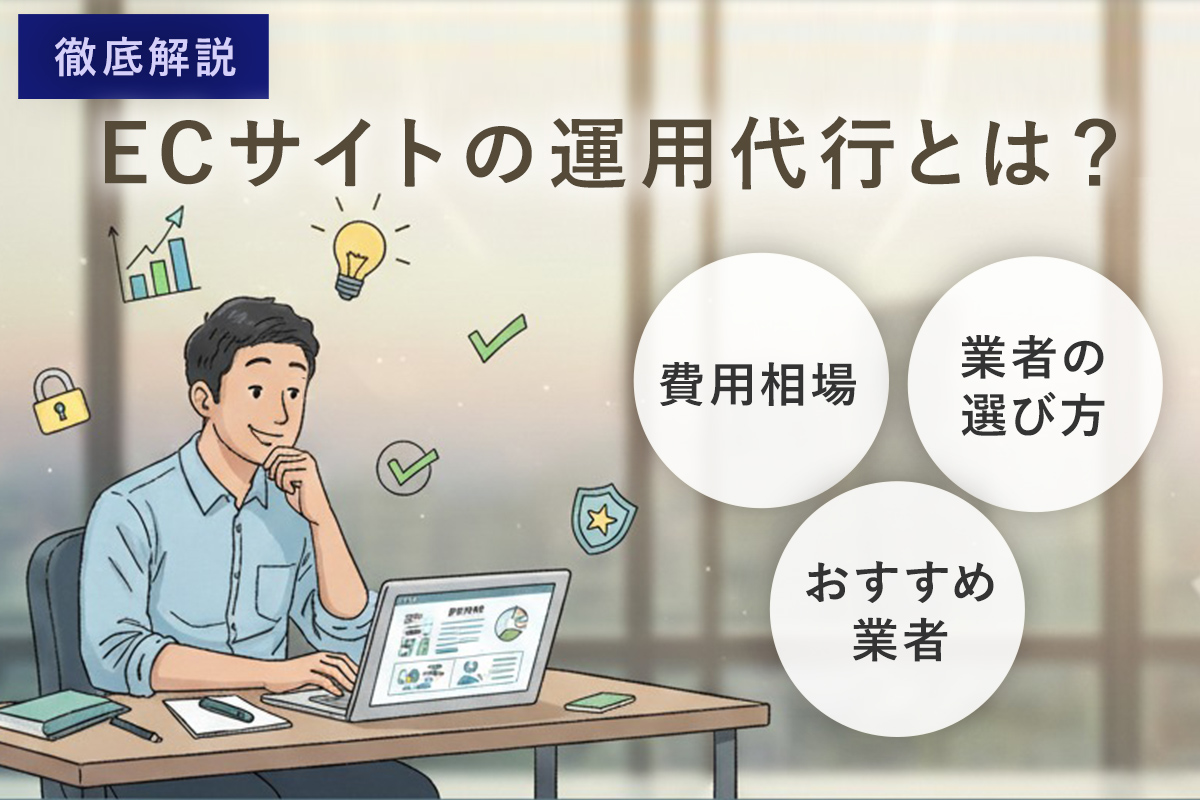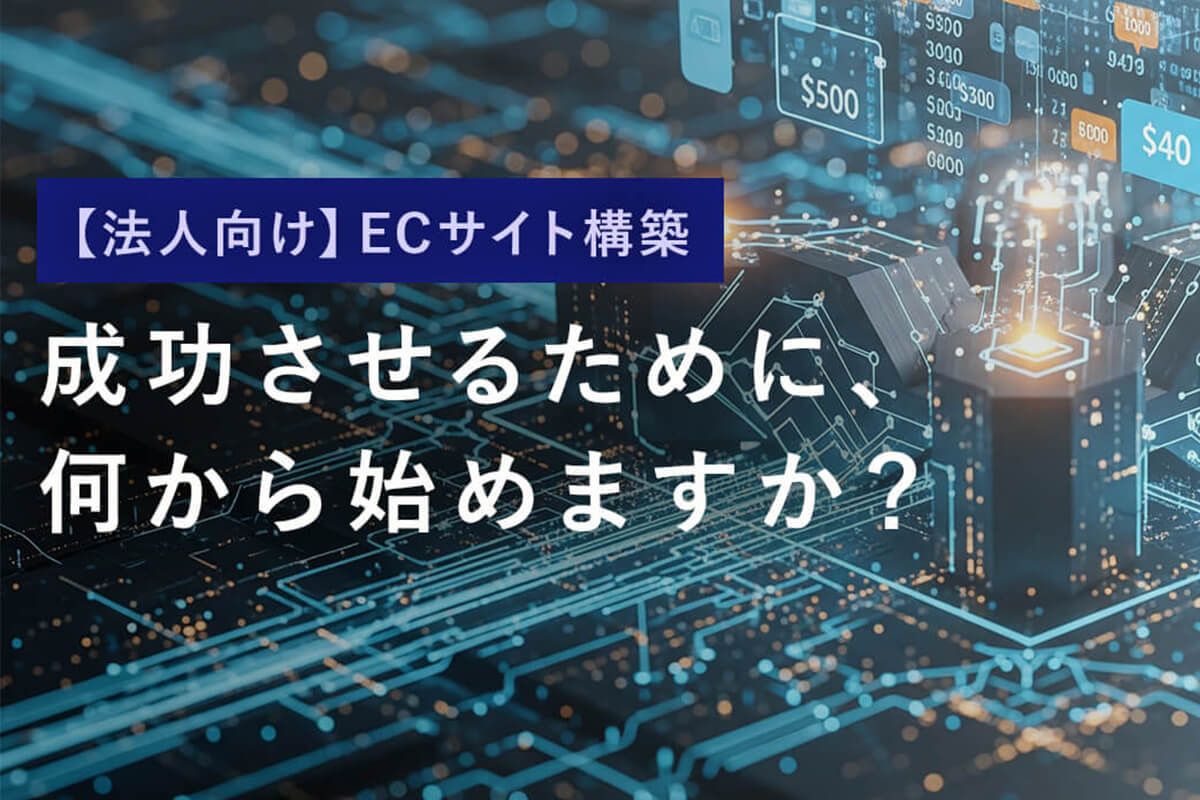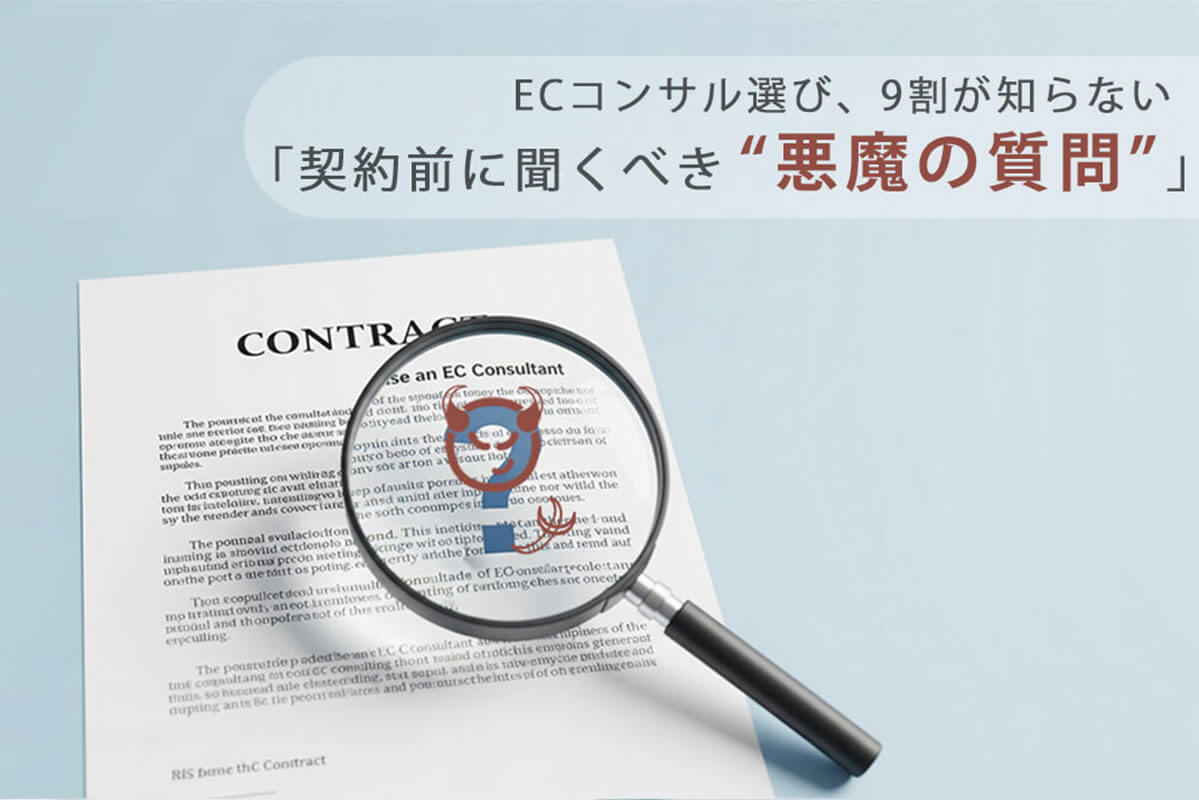ECサイトを無料で作成する方法|成長まで見据えた初心者でも失…
「ECサイト始めてみたいけど、いきなり何十万円もかけるのは不安…」そんな方へ。
実は今の時代、初期費用0円でもECサイトは始められます。
「BASE」や「STORES」など、初心者でも使いやすい無料サービスの進化により、スマホひとつでネットショップを立ち上げることが可能です。
この記事では、ECサイト制作10年以上の実績を持つキノスラが、
・無料でECサイトを作る3つの方法
・各無料サービスの本音比較(メリット・デメリット)
・無料から本格サイトへ移行タイミング
・よくわからなくなった時の相談先
まで、段階的成長を見据えた"本当に使える情報"をお届けします。
ECサイトを無料で作成できる3つの方法
ECサイトを無料で作成する方法は、大きく分けて3つあります。それぞれの特徴を理解して、最適な方法を選びましょう。
① 無料ASPカートを利用する(BASE、STORES、Square等)
最も手軽で初心者におすすめの方法です。アカウント登録から数時間でECサイトを開設でき、基本的に技術的な知識は不要です。デザインテンプレートを選び、商品を登録するだけで、すぐに販売を始められます。
代表的なサービス:
サービス名公式サイトへのリンク
BASEhttps://thebase.com/
STOREShttps://stores.fun/
Squarehttps://squareup.com/jp/ja
カラーミーショップ(フリープラン)https://help.shop-pro.jp/hc/ja
② オープンソースで自作する(EC-CUBE、Magento等)
プログラミング知識がある方向けの方法です。システム自体は無料ですが、サーバー代や開発工数がかかるため、実質的には有料と考えるべきでしょう。カスタマイズの自由度は最も高いですが、セキュリティ対策やアップデート作業も自己責任となります。
代表的なシステム:
サービス名公式サイトへのリンク
EC-CUBEhttps://www.ec-cube.net/
Magento Open Sourcehttps://magento-opensource.com/
Drupal Commercehttps://drupalcommerce.org/
③ WordPressプラグインを使う(WooCommerce等)
既存のWordPressサイトにEC機能を追加したい場合に有効な方法です。コンテンツマーケティングとECを統合できるメリットがありますが、決済連携やセキュリティ設定には一定の技術知識が必要です。
代表的なプラグイン:
サービス名サイトへのリンク
WooCommercehttps://ja.wordpress.org/plugins/woocommerce/
Welcarthttps://ja.wordpress.org/plugins/usc-e-shop/
Easy Digital Downloadshttps://ja.wordpress.org/plugins/easy-digital-downloads/
【比較表】3つの方法を徹底比較
方法難易度初期費用月額費用カスタマイズ性おすすめ度代表的なサービスとURL
無料ASP★☆☆0円0円中★★★BASE:https://thebase.com/
オープンソース★★★0円サーバー代高★☆☆EC-CUBE:https://www.ec-cube.net/
WordPress★★☆0円サーバー代中〜高★☆☆WooCommerce:https://ja.wordpress.org/plugins/woocommerce/
この記事では、最も現実的で成果が出やすい①無料ASPカートを中心に解説していきます。
無料で使えるECサイト作成サービス徹底比較【5選】
ここからは、初期費用・月額費用が無料で使えるECサイト作成サービスを、実際の使用感も踏まえて徹底比較します。
BASE(ベイス)|開設実績No.1の王道サービス
BASEの基本情報
項目内容
初期費用0円
月額費用0円 (スタンダードプラン: 月額980円)
決済手数料3.6% + 40円 + サービス利用料3.0% (スタンダードプランは2.9%)
商品登録数無制限
デザインテンプレート80種類以上 (無料・有料)
独自ドメインスタンダードプラン以上で利用可能
⭕️BASEのメリット
✓ 開設数240万店以上の圧倒的実績と信頼性
国内最大級のネットショップ開設数を誇り、個人事業主から法人まで幅広く利用されています。
✓ 直感的な操作で最短30分で開設可能
専門知識がなくても、画面の指示に従うだけでショップを開設できます。「今日思い立って、今日オープン」も可能です。
✓ Instagram連携など集客機能が充実
Instagram Shopping機能やTikTok連携など、SNS集客に強いのが特徴。特に若年層向け商材と相性が良好です。
✓ App機能で拡張性が高い
80種類以上の拡張機能(App)が用意されており、必要に応じて機能を追加できます。送料詳細設定、予約販売、デジタルコンテンツ販売など、多様なニーズに対応。
❌️BASEのデメリット
✗ 決済手数料が実質6.6%と高め
フリープランでは「決済手数料3.6% + 40円 + サービス利用料3.0%」がかかり、実質6.6%+40円の負担となります。月商50万円なら月額約3.3万円が手数料で消える計算です。
✗ 独自ドメイン利用は有料プラン必須
フリープランでは「〇〇〇.thebase.in」というサブドメインのみ。独自ドメインを使いたい場合はスタンダードプラン(月額980円)への加入が必要です。
✗ SEO対策の自由度が限定的
HTMLの直接編集ができないため、細かなSEO調整には限界があります。Google検索からの集客を主軸にするには工夫が必要です。
✗ デザインカスタマイズに制限あり
テンプレートベースのため、完全オリジナルのデザインは困難。ブランドイメージを細部まで表現したい企業には物足りない可能性があります。
こんな人におすすめ
✅️とにかく今日・今すぐ始めたい人
✅️まずは月10〜30万円程度の売上を目指す人
✅️SNS集客をメインにしたい人(特にInstagram、TikTok)
✅️ハンドメイド作品や少量多品種の商材を扱う人
BASEの公式サイトを見る:https://thebase.com/
STORES(ストアーズ)|デザイン性重視派に人気
STORESの基本情報
項目内容
初期費用0円
月額費用"0円 (スタンダードプラン:月額2,178円)"
決済手数料5.0%(フリープラン) / 3.6%(スタンダードプラン)
商品登録数無制限
デザインテンプレート48種類(全て無料、デザイン性高)
独自ドメインスタンダードプラン以上で利用可能
⭕️STORESのメリット
✓ 決済手数料がBASEより安い
フリープランでも決済手数料5.0%のみ。BASEの実質6.6%と比較すると、売上が伸びるほど差が大きくなります。月商50万円なら月額2.5万円(BASE比で8千円の削減)。
✓ デザインテンプレートの質が高い
全48種類のテンプレートは、どれもプロのデザイナーが手がけた洗練されたデザイン。アパレル・雑貨・コスメなど、ビジュアルが重要な業種に最適です。
✓ 代引き決済に対応
BASEでは利用できない代金引換決済が使えます。高齢者層やクレジットカードを持たない顧客層にもアプローチ可能です。
✓ 予約販売・定期販売機能あり
予約注文や定期購入(サブスクリプション)機能が標準装備。D2Cブランドや頒布会ビジネスにも対応できます。
❌️STORESのデメリット
✗ HTML/CSS編集不可でカスタマイズ性が低い
テンプレートのカスタマイズはGUI操作のみ。コードを直接編集できないため、細かなデザイン調整ができません。
✗ 月売上30万円超えるとスタンダード移行推奨
フリープランの5%手数料は、売上が増えると重い負担に。月商30万円で1.5万円、50万円で2.5万円が手数料として消えます。
✗ App的な拡張機能が少ない
BASEのような豊富な拡張機能(App)がなく、標準機能のみで運用する形になります。特殊な機能が必要な場合は不向きです。
こんな人におすすめ
✅️おしゃれなデザインにこだわりたい人
✅️アパレル・雑貨・コスメ系の商材を扱う人
✅️代引き決済が必要な人(特に高単価商材)
✅️手数料を少しでも抑えたい人
STORESの公式サイトを見る:https://stores.fun/
Square オンラインビジネス|実店舗連携が強み
Squareの基本情報
項目内容
初期費用0円
月額費用"0円 (プロフェッショナルプラン:月額3,375円)"
決済手数料3.6%
商品登録数無制限
デザインテンプレート無料・有料テンプレートあり
独自ドメイン無料プランでも利用可能
⭕️Squareのメリット・特徴
✓ 実店舗のPOSレジと完全連携
Squareの最大の強みは、実店舗とECの在庫・顧客情報を一元管理できる点。既にSquare POSを使っている店舗なら、シームレスにEC展開が可能です。
✓ 決済手数料がシンプル
3.6%のみで、BASE・STORESのような複雑な料金体系がありません。売上計算がシンプルで、コスト管理がしやすいのが特徴です。
✓ 独自ドメインが無料プランでも使える
BASE・STORESと異なり、無料プランでも独自ドメインが利用可能。SEO的にも有利です。
❌️Squareのデメリット
✗ デザインテンプレートが少ない(約10種類)
✗ 日本特有の決済方法(代引き等)に非対応
こんな人におすすめ
✅️実店舗を持っていて、EC展開したい人
✅️在庫管理を一元化したい人
✅️シンプルな料金体系を好む人
Squareの公式サイトを見る:https://squareup.com/jp/ja
Cafe24|本格派向けの無料サービス
Cafe24の基本情報
項目内容
初期費用0円
月額費用0円
決済手数料2.75%〜4.5%(決済方法により変動)
商品登録数無制限
デザインテンプレート無料・有料テンプレートあり
独自ドメイン無料で利用可能
⭕️Cafe24のメリット・特徴
✓ 決済手数料が業界最安水準
✓ カスタマイズ性が高い(HTML/CSS編集可能)
✓ 越境EC(海外販売)に強い
❌️Cafe24のデメリット
✗ 管理画面が複雑で初心者には難しい
✗ 日本語サポートがやや弱い(韓国発のサービス)
こんな人におすすめ
✅️ある程度EC経験がある人
✅️手数料を徹底的に抑えたい人
✅️将来的に海外展開も視野に入れている人
Cafe24の公式サイトを見る: https://www.cafe24.co.jp/
メルカリShops|圧倒的な集客力が魅力
メルカリShopsの基本情報
項目内容
初期費用0円
月額費用0円
販売手数料10%(メルカリ本体と同じ)
商品登録数無制限
デザインテンプレート-
独自ドメイン-
⭕️メルカリShopsのメリット
✓ 月間2,200万人以上のメルカリユーザーにリーチ
最大のメリットは、メルカリアプリ内の膨大なユーザーベースに直接アプローチできること。集客コスト0円で顧客に出会えます。
✓ 設定が超シンプル
メルカリの出品経験があれば、ほぼ同じ感覚で使えます。ECサイト構築の知識は一切不要。
❌️メルカリShopsのデメリット
✗ 販売手数料10%は最も高い
✗ 独自ドメインが使えない(メルカリ内のショップ扱い)
✗ ブランディングが困難(メルカリの枠内での運営になるため)
こんな人におすすめ
✅️とにかく手軽に始めたい人
✅️集客に自信がない人
✅️メルカリで既に販売実績がある人
メルカリShopsの公式サイトを見る:https://jp.mercari.com/shops
【総合比較表】どの無料ECサービスを選ぶべき?
サービス初期費用月額費用決済手数料独自ドメイン(無料)初心者向けおすすめ用途
BASE0円0円〜6.6%+40円×◎SNS集客×多品種
STORES0円0円〜5.0%×◎デザイン重視
Square0円0円〜3.6%○○実店舗連携
Cafe240円0円2.75%〜○△本格派・越境EC
メルカリShops (モール型)0円0円10%×◎超手軽スタート
もし迷ったら、BASE or STORESから始めるのが無難です。
どちらも初心者に優しく、十分な機能を備えています。
無料ECサイト作成の7ステップ【BASE/STORESで実践】
ここからは、BASE・STORESを例に、実際にECサイトを開設する手順を解説します。
初めての方でも、この流れに沿えば迷わず開設できます。
STEP1: サービス選定とアカウント登録(所要時間:5分)
まずはBASEまたはSTORESの公式サイトにアクセスし、アカウント登録を行います。
必要な情報:
・メールアドレス
・パスワード
・ショップURL(後で変更不可なので慎重に)
登録自体は5分程度で完了します。メールアドレス認証を済ませれば、すぐに管理画面にアクセスできます。
STEP2: ショップ基本情報の設定(所要時間:20分)
次に、ショップの基本情報を入力していきます。
設定項目ポイント/内容
ショップ名覚えやすく、商材が連想できる名前が理想
ショップ説明文検索結果にも表示されるため、キーワードを意識
運営者情報特定商取引法に基づく表記(住所、電話番号等)
プライバシーポリシーテンプレートが用意されているので活用
返品・交換ポリシートラブル防止のため明確に記載
💡ポイント
運営者情報は法律で表示が義務付けられています。
自宅住所を公開したくない場合は、バーチャルオフィスの活用も検討しましょう。
STEP3: デザインテンプレート選択とカスタマイズ(所要時間:30分)
ショップの"顔"となるデザインを選びます。
【選び方のコツ】
✅️商材のイメージに合うか:
アパレルならスタイリッシュ、食品なら温かみのあるデザイン
✅️商品写真が映えるか:
写真の配置やサイズ感を確認
✅️スマホでの見え方:
購入の70%以上はスマホから!
テンプレートを選んだら、ロゴ・カラー・フォントをカスタマイズできます。
この段階では完璧を目指さず、まずは「及第点」を目指しましょう。
後からいくらでも変更できます。
STEP4: 商品登録(所要時間:1商品あたり15分)
いよいよ商品を登録していきます。
登録項目内容/ポイント
商品名検索を意識したキーワード含有
商品写真最低3枚、できれば5〜7枚
価格税込表示が基本
在庫数正確に管理
商品説明文サイズ、素材、使い方、注意事項を詳しく
カテゴリー・タグ検索されやすくするため重要
📸商品写真のコツ:
・明るく、ピントが合った写真
・複数角度から撮影
・サイズ感がわかるよう比較対象を入れる
・実際の使用シーンも1枚は入れる
重要:
商品写真の質が売上を大きく左右します。
スマホ撮影でも構いませんが、照明と背景には気を配りましょう。
STEP5: 決済方法・配送設定(所要時間:20分)
顧客がスムーズに購入できるよう、決済と配送を設定します。
決済方法の選択:
・クレジットカード(必須)
・コンビニ決済
・銀行振込
・キャリア決済
・代金引換(STORESのみ)
配送設定:
・配送業者の選定(ヤマト、佐川、日本郵便等)
・送料の設定(全国一律 or 地域別)
・配送日数の目安
・送料無料ラインの設定(例:5,000円以上購入で送料無料)
💡送料設定のポイント
「送料無料」は購入率を大きく上げる要素です。商品価格に送料を含めて「送料無料」とする戦略も有効です。
STEP6: プライバシーポリシー等の法務対応(所要時間:30分)
ECサイトには、法律的に必須となる表記事項があります。お客様が安心してお買い物できるよう、また、ご自身も安心して法を遵守した運用ができるようにしましょう。
必須ページ:
・特定商取引法に基づく表記
・プライバシーポリシー
・利用規約
・返品・交換ポリシー
BASE・STORESともテンプレートが用意されているので、それをベースに自社の状況に合わせて調整しましょう。
💡食品・酒類を販売する場合の注意点
🍽️食品を販売する場合:
食品衛生法上「食品衛生責任者」の資格と「食品衛生法に基づく営業許可」が必要です。
🍷酒類を販売する場合:
「一般酒類小売業販売免許」か「通信販売酒類小売業免許」のどちらかが必要です。
また、「酒類販売管理者標識」情報もサイト内に掲載しましょう。
STEP7: テスト購入で動作確認(所要時間:30分)
公開前に、必ず自分で購入テストを行います。
確認項目:
・商品選択から決済完了までの流れ
・注文確認メールが届くか
・決済が正常に処理されるか
・スマホでの表示・操作感
・購入完了後の管理画面での注文確認
問題がなければ、いよいよ公開です!
無料だからこそ、手抜き厳禁!
ランニングコストが少ないとはいえ、しっかり売上を作っていくためには、手抜き厳禁です。
特に商品写真・説明文のクオリティは売上に直結します。
「商品の魅力が伝わる写真の撮り方がわからない」
「商品説明文の書き方に自信がない」
「そもそも何から始めればいいかわからない」
こんな不安がある場合は、最初だけプロに相談するのも賢い選択です。
キノスラでは、ECサイト開設の初期サポートも行っています!
お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。
→ 株式会社キノスラ|お問い合わせはこちら
無料でECサイトを作成するメリット・デメリット【正直に語ります】
無料でECサイトを始められるのは魅力的ですが、メリットだけでなく、デメリットも正しく理解した上で判断することが重要です。
EC制作10年以上の経験から、本音でお伝えします。
ECサイト無料作成のメリット:無料だからこその強み
✓ 初期投資ゼロでリスク最小化
従来のECサイト構築には数十万〜数百万円の初期費用が必要でした。
しかし無料サービスなら、初期費用0円でスタートできます。
「売れるかわからない商品」をテスト販売したり、副業として小さく始めたりする場合、初期投資リスクがないのは大きな安心材料です。
✓ 技術知識不要で即日スタート可能
HTMLやCSSの知識がなくても、画面の指示に従うだけでプロ並みのECサイトが作れます。「思い立ったその日に開業」も可能です。
従来は制作会社に依頼して数ヶ月待つ必要がありましたが、今はそのハードルが完全になくなりました。
✓ 小規模ならランニングコスト実質0円
月商10〜30万円程度の規模なら、決済手数料以外のコストはほぼ発生しません。サーバー代、保守費用、セキュリティ対策費など、本格的なサイトでは必要なコストが一切不要です。
✓ 失敗してもダメージ小(撤退しやすい)
「EC事業がうまくいかなかった」場合でも、金銭的ダメージはほぼゼロ。気軽に始められて、気軽に撤退できる。これも無料サービスの大きなメリットです。
ECサイト無料作成のデメリット:成長とともに見えてくる限界
【短期的デメリット】
✗ デザイン・機能のカスタマイズに限界
テンプレートベースのため、「ここだけ変更したい」という細かな要望に応えられないことがあります。
特に、ブランドイメージを細部まで表現したい企業にとっては、この制約が大きなストレスになります。
✗ 独自ドメインが使えない(または有料)
BASEやSTORESの無料プランでは、「yourshop.thebase.in」のようなサブドメインしか使えません。
独自ドメイン(例:www.yourshop.com)を使うには有料プランへのアップグレードが必要。SEO的にも、ブランディング的にも、独自ドメインがないのは不利です。
✗ 集客は完全に自力 (プラットフォームの恩恵なし)
楽天市場やAmazonのようなモール型ECと異なり、BASE・STORESは「場所を貸してくれるだけ」。集客は完全に自力で行う必要があります。
SNS、広告、SEO…どれかの集客チャネルを確立しないと、「作ったけど誰も来ない」状態になります。
【見落としがち!中長期的デメリット】
✗ 売上が伸びるほど手数料負担が重くなる
これが最も見落とされがちな問題です。
具体例で見てみましょう。
月商手数料(6.6%)年間手数料
10万円"6,600円 "約8万円
30万円"19,800円 "約24万円
50万円"33,000円 "約40万円
100万円"66,000円 "約80万円
月商50万円で年間40万円、月商100万円なら年間80万円が手数料で消えます。
一方、本格的なECサイト+決済代行会社の組み合わせなら、決済手数料は2.5〜3.5%程度。月商100万円でも年間30〜42万円です。
つまり、売上が伸びるほど、無料サービスの方が高コストになるのです。
✗ データ資産が制限される
顧客データの活用に制約があるのも大きな問題です。
- 顧客の詳細な購買履歴分析が困難
- CRM(顧客関係管理)ツールとの連携に制限
- メールマーケティングの自由度が低い
- 他サービスへのデータ移行が困難
EC事業において、顧客データは最も重要な資産。このデータを十分に活用できないのは、成長の大きな足かせになります。
✗ マーケティング施策の自由度が低い
本格的なEC運営では、以下のような施策が重要になります:
- A/Bテスト(複数パターンの効果検証)
- カゴ落ちメール(購入直前で離脱した顧客へのリマインド)
- 会員ランク制度(ゴールド会員は10%OFF等)
- クロスセル・アップセル施策
- RFM分析に基づくセグメント配信
しかし、無料サービスではこれらの高度な施策がほとんど実現できません。
💬 EC運営10年、キノスラスタッフの本音
無料サービスは、まずはスモールスタートで始めたい方の"EC入門"としては最適解です。
ただし、月商50万円を超えたあたりから、手数料負担と機能制約が重くのしかかってくるのが事実です。
適切なタイミングで、無料サービスから売上に見合った有料サービスに切り替えないと、
"売上は伸びているのに、手元に残る利益が増えない"
"やりたいマーケティング施策が実現できない"
という状況に陥ります。
大切なのは、成長段階に応じた無料サービスからの"卒業タイミング"を見極めること。
そのタイミングを逃すと、機会損失が膨らんでいきます。
【重要】ECサイト無料作成サービスから"卒業"すべき5つのサイン
「そろそろ無料サービスを卒業すべきかも?」
そう感じたら、以下のチェックリストで診断してみてください。
📊 無料サービスの卒業タイミング診断
当てはまる✅️の数をカウントしてみましょう。
✅️サイン1: 月商50万円を安定的に超えている
月商50万円は、無料サービス卒業を検討すべき重要なラインです。
理由:
・BASE手数料(6.6%)なら月額3.3万円、年間約40万円
・本格サイト+決済代行(3.0%)なら月額1.5万円、年間18万円
・差額年間22万円を、サイト改善や広告に投資できる
単発ではなく「安定的に」50万円を超えているなら、移行を検討すべきタイミングです。
✅️サイン2: 手数料が利益を圧迫している
粗利率30%の商品を販売している場合、決済手数料6.6%は実質的に粗利の22%を占めます。
計算例:
項目金額/内訳
売上50万円
原価35万円
粗利 (粗利率30%)15万円
手数料3.3万円
手残り11.7万円 (粗利の22%が手数料に相当)
この表は、月商50万円、粗利率30%の商品を販売し、決済手数料が6.6%かかる場合のシミュレーションです。
これに広告費や人件費が加わると、「売れば売るほど苦しい」状態になりかねません。
✅️サイン3: やりたい施策が実現できない
以下のような施策を実現したくなったら、無料サービスの限界です。
施策名内容/具体例
会員ランク制度ゴールド会員は常時10%OFFなど、顧客ロイヤリティ向上
ポイント戦略購入金額の5%ポイント還元など、再購入を促進
カゴ落ちメール購入直前で離脱した人への自動リマインド
ステップメール購入後7日目、14日目に自動配信など、フォローアップ施策
クロスセル施策「この商品を買った人はこんな商品も」といった合わせ買い提案
定期購入の柔軟な設定スキップ、周期変更など、顧客の利便性を高める機能
これらはリピート率・LTVを高める重要施策ですが、無料サービスでは実現困難です。
✅️サイン4: デザイン・機能の限界を感じている
・ブランドイメージが表現できない
→ テンプレートでは「自分たちらしさ」が出せず、競合との差別化が困難
・スマホ最適化に不満
→ 細かな導線設計ができず、購入率が伸び悩む
・商品ページのカスタマイズができない
・商品特性に応じた見せ方ができない
「もっとこうしたいのに」という不満が増えてきたら、移行を検討すべきサインです。
✅️サイン5: 複数チャネル展開を始めた
- 自社サイト(BASE/STORES)
- 楽天市場
- Yahoo!ショッピング
- Amazon
このように複数チャネルで販売を始めると、「一元管理」の必要性が急速に高まります。
課題:
・在庫連携ができず、売り越しリスク
・顧客データがバラバラで、統合分析ができない
・受注処理が各チャネルごとで、業務負担大
本格的なECサイトなら、在庫連携システムやOMS(受注管理システム)との連携が可能です。
✅ 診断結果
3つ以上当てはまる → 本格サイト移行の検討時期です。
5つ当てはまる → 移行を強く推奨します。
ECサイト無料→有料サービスへの移行タイミングの目安まとめ
指標移行検討ライン移行推奨ライン
月商50万円100万円
取扱商品数30〜50点100点以上
運営期間6ヶ月1年以上
リピート率20%30%以上
月間セッション数"5,000""10,000以上 "
ECサイト無料作成サービスから本格的なECサイトに移行する2つの選択肢
無料サービスから成長した後、次のステップとして考えられる選択肢は主に3つです。それぞれの特徴を理解して、自社に最適な選択をしましょう。
【選択肢1】有料ASPにアップグレード
代表的なサービス:
サービス名月額費用
Shopify月額33ドル〜
カラーミーショップ 有料プラン"月額4,950円〜 "
MakeShop"月額12,100円〜 "
futureshop"月額22,000円〜 "
費用感
項目費用/レンジ
初期費用0〜10万円
月額費用"3,000円〜3万円 "
決済手数料3.0〜3.6%
有料ASPのメリット
✓ 移行コストが比較的低い
初期費用が抑えられるため、中小規模でも導入しやすい
✓ 機能拡張が柔軟
アプリ連携で必要な機能を後から追加できる
✓ 保守運用が楽
サーバー管理やセキュリティ対策はサービス側が対応
有料ASPのデメリット
✗ カスタマイズには限界がある
根本的なシステム変更は不可
✗ 月額費用が継続的に発生
売上がなくても固定費が発生
こんな企業におすすめ
✅️月商50〜200万円の規模
✅️まずは固定費を抑えたい
✅️技術者を社内に抱えていない
【選択肢2】ECパッケージを導入
代表的なサービス:
・ecbeing
・EC-ORANGE
・SI Web Shopping
・ebisumart
費用感
項目費用/レンジ
初期費用100〜500万円
月額保守費用5〜20万円
決済手数料2.5〜3.5%
ECパッケージのメリット
✓ 本格的な機能が標準装備
大規模ECに必要な機能が最初から揃っている
✓ カスタマイズの自由度が高い
自社の業務フローに合わせた調整が可能
✓ 大量トラフィックに対応
月間数百万PVでも安定稼働
ECパッケージのデメリット
✗ 初期コストが高い
最低でも数百万円の投資が必要
✗ 開発期間が長い
稼働まで3〜6ヶ月かかる
✗ 保守費用が継続的に発生
月額5〜20万円の固定費
こんな企業におすすめ
✅️月商500万円以上
✅️独自の業務フローがある
✅️中長期的な成長を見据えている
まとめ|ECサイト無料作成サービスは"始める"に最適、"伸ばす"には戦略が必要
無料でECサイトを作ることは、もはや当たり前の選択肢です。BASE・STORESを使えば、今日からでも始められます。
ただし、「無料で始めること」=「無料のまま成長すること」ではないことを忘れないでください。
◆ 月商30万円まで → 無料サービスで十分
・初期投資リスクを最小化
・試行錯誤しながら学ぶ段階
◆ 月商50万円超え → 移行を検討すべきタイミング
・手数料負担が重くなり始める
・やりたい施策が実現できなくなる
◆ 月商100万円超え → 本格サイトへの移行推奨
・手数料差額で年間数十万円の差
・データ資産の活用が成長の鍵に
成長するほど、手数料と機能制約が足かせになります。
結局何を選べば良いの?迷ったらキノスラにご相談ください!
私たちCynosura(キノスラ)は、 EC特化10年以上の実績 を持つ制作会社です。
豊富な業界実績
業界特有の要件を熟知しているため、「あるある」の落とし穴を回避できます。
キノスラは、化粧品・健康食品、食品・スイーツ、美容器具、インテリア・ファッションなど、幅広い業界のECサイトを手掛けています。
ワンストップ対応
ECサイト制作・運用に必要なこと全般、社内で対応できるため、窓口が一本化され、スピーディーな対応が可能です。
項目内容
コンサルティング戦略設計、要件定義
制作デザイン、システム構築
運用代行楽天・Yahoo等の運用代行も可能
マーケティング広告運用、SEO対策
段階的成長を支援いたします!
予算にあわせて「今必要な機能から始めて、段階的に拡張する」設計も得意です。
「無料サービスの次のステップ、どうしたらいい?」
そんな疑問をお持ちの方は、まず 無料相談 を。
もちろん、無理に移行を勧めることはしません。
貴社の現状・目標をヒアリングし、
・今すぐ移行すべきか
・あと半年様子を見るべきか
・どの選択肢が最適か
を、売上データを見ながら一緒に判断します。
お問い合わせ
ECサイト制作・コンサルティングに関するお見積り、サービスに関するご相談など、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ